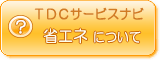
説明義務制度は、令和元年5月17日に改正建築省エネ法が公布され、2年以内施行の内容として新たに追加された制度であり、
300㎡未満の住宅建築物に対し、省エネ基準への適否等の説明を義務づけています。
300㎡未満の住宅建築物に対し、省エネ基準への適否等の説明を義務づけています。
小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度
制度の概要
〇 建築主は、省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(努力義務)
〇 小規模住宅・建築物(300 ㎡未満の住宅・建築物)の新築等に係る設計の際に、次の内容について、
建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務づける。
〇 建築士法に基づき、都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立ち入り検査が可能。
※上記内容は、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思表明があった場合には適用されません。
〇 小規模住宅・建築物(300 ㎡未満の住宅・建築物)の新築等に係る設計の際に、次の内容について、
建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務づける。
① 省エネ基準への適否
② 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
〇 説明に用いる書面を建築士事務所の保存図書に追加予定。(建築士法省令を改正予定)② 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
〇 建築士法に基づき、都道府県等は建築士事務所に対する報告徴収や立ち入り検査が可能。
※上記内容は、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思表明があった場合には適用されません。
手順フロー
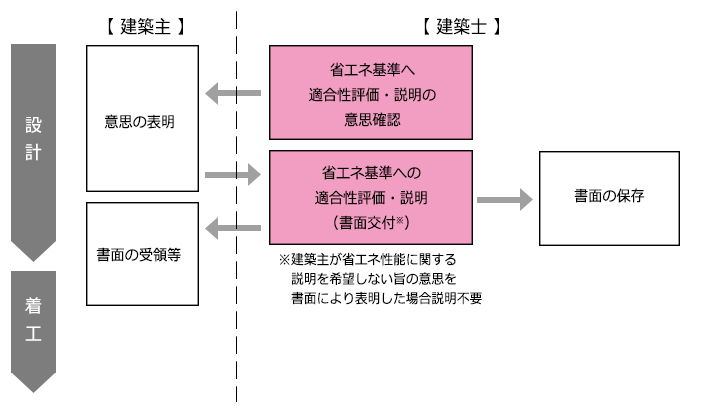
経過措置
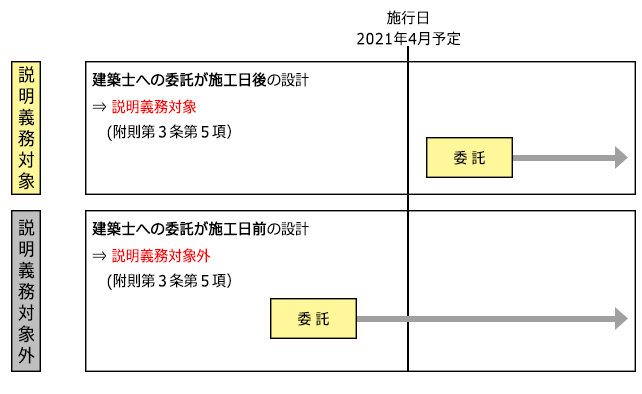
説明書のイメージ
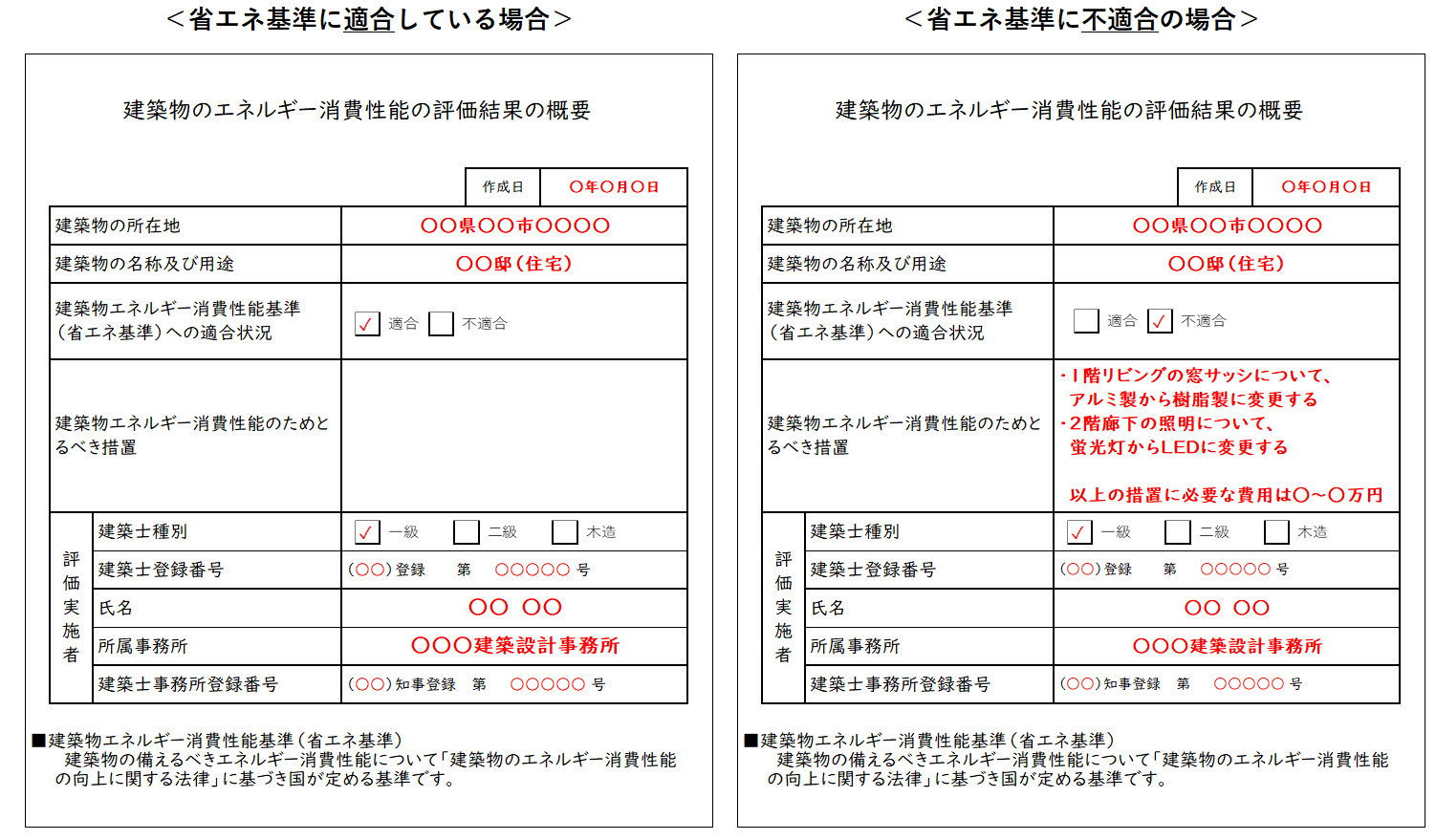
届出・説明の対象範囲
[ 新築 ]
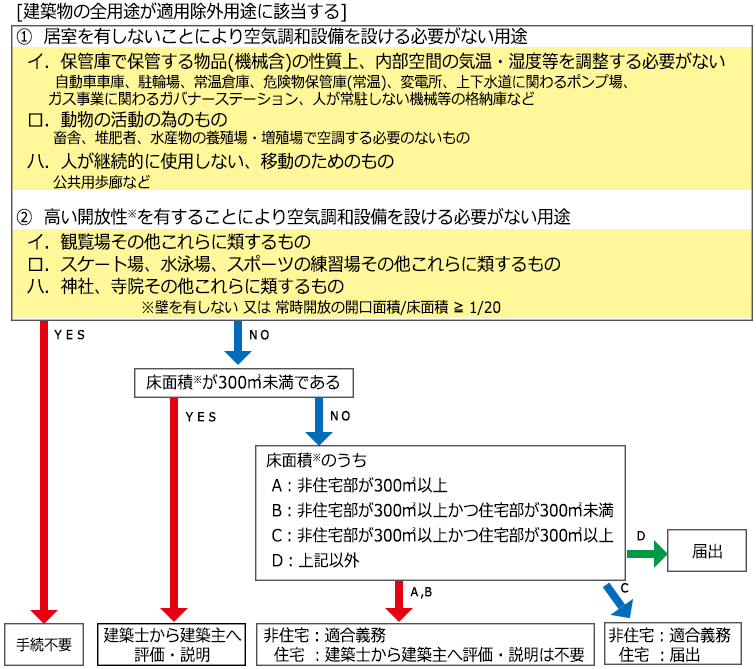
建築物の規模が10㎡以上
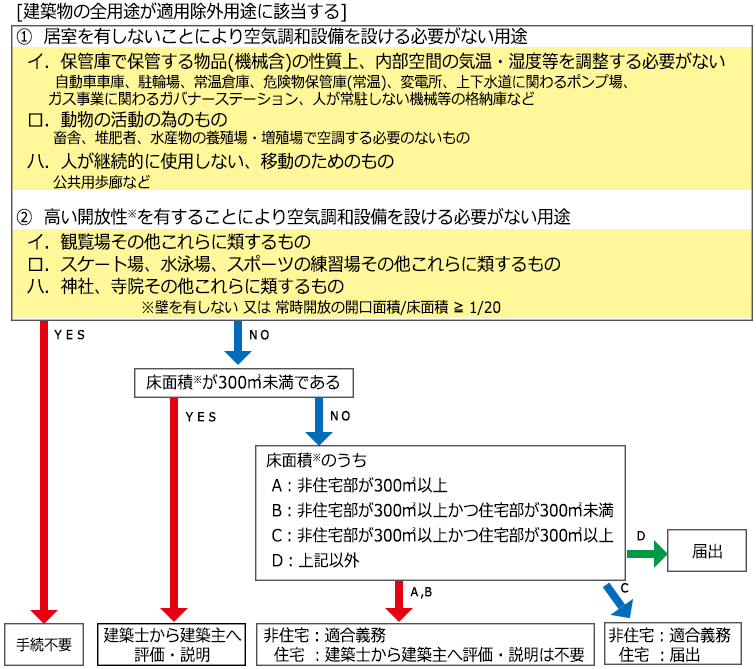
※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた床面積とする
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
[ 増改築 ]
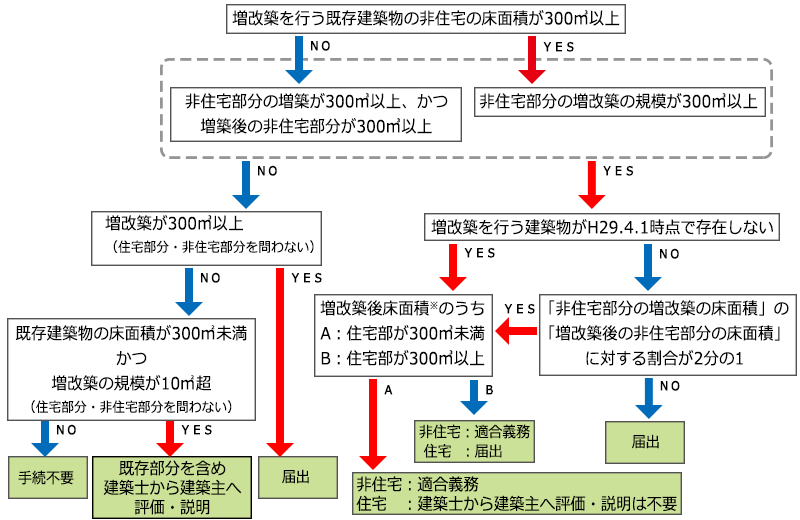
増築の規模が10㎡以上
(住宅部分・非住宅部分を問わない)
(住宅部分・非住宅部分を問わない)
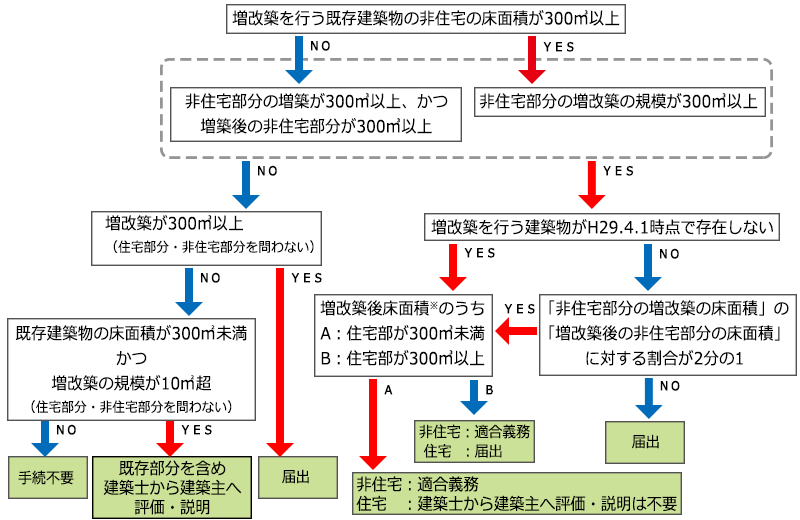
※ここで指す床面積とは下記を満たす高い開放性を有する面積を除いた面積
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
・空調設備が設置されない最小限の部分である
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している(常時開放の開口面積/床面積 ≧ 1/20)
省エネ基準適否確認計算手法
下記の表の青枠部が説明義務制度にて使用可能な計算ツールです。
住宅・建築物の省エネ性能の評価方法の分類

| ※ | 標準入力法、モデル建物法、小規模モデル建物法、外皮計算用Excelシート、WEBプログラム、モデル住宅法、フロア入力法とはH28国土交通省告示【第265号】に規定する評価方法を指す。どちらも国立研究開発法人『建築研究所』WEB公開の省エネルギー基準に準拠したプログラム又はExcelデータ等により評価する。 |
| ※1 | 共同住宅等の一次エネの算出にあたっては、住宅部分の設計一次エネ消費量、基準一次エネ消費量(又は誘導基準一次エネ消費量、特定建設工事業者基準一次エネ消費量)の算出において、共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)を評価しない方法が可能(2019.11施行)。 ただし、低炭素認定においては、共用部分の評価を必須化(2022.10施行)。 |
| ※2 | 共用部分を計算しない評価方法の場合のみ適用可能。低炭素認定においては共同住宅等の共用部が無い場合のみ適用可能。 |
| ※3 | BEST省エネ基準対応ツールとは基準省令第1条第1号及び第10条第1号に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法。又、BEST省エネ基準対応ツールの適用については提出先機関の審査体制による。適用可能の判断を事前確認する必要がある |
| ※4 | 複数建築物の認定においては使用不可。 |
| ※5 | 仕様基準とはH28国土交通省告示【第266号】に規定する評価方法を指す。誘導基準とは国土交通省告示【第1106号】に規定する評価方法を指す。 |
| ※6 | 地方公共団体の条例において、一定規模以上の建築物に省エネ基準の必要な事項を附加している場合は、当該条例の定める建築物について対象になる。 |
| ※7 | 別途、結露防止対策の基準に適合することが必要。 |
| ※8 | ZEH Oriented、ZEH-M Oriented(共用部分が無い場合)のみ使用可能。 |
| ※9 | 省エネ性能の確認は可能だが、再エネを含んだ評価について別途標準計算で確認する必要。 |
| ※10 | 断熱等性能等級4又は外皮が仕様基準に適合することが必要。 |
| ※11 | 断熱等性能等級5又は外皮が誘導仕様基準に適合することが必要。 |
参考(国交省Q&A)
<対象>
<その他>
| Q: | 床面積が300㎡未満の住宅部分を含む特定建築物について、当該住宅部分は所管行政庁による指示・命令等の対象とはならないが、説明義務等は生ずることとなるのか。 |
| A: | 特定建築物は説明義務制度の対象とはなりません。 |
| Q: | 増改築工事に係る説明義務は必要となるのか。 |
| A: | 適合義務もしくは届出の対象とならない300㎡未満の住宅及び非住宅の増改築工事については、説明義務制度の対象となります。なお、当該増改築の規模が10㎡未満の場合については、説明義務制度の対象外となります。 |
<その他>
| Q: | 説明を行わなかった場合、指導や罰則を受けることがあるのか。 |
| A: | 説明義務制度に基づく説明を行わなかった場合、建築士法に基づく処分の対象となる可能性があります。 |
| Q: | 将来的には小規模住宅・建築物も適合義務化されるのか。 |
| A: | まずは改正建築物省エネ法に盛り込まれた施策を的確に推進し、省エネ性能の向上に取り組み、これらの施策の推進状況や適合率の向上の状況等を踏まえて、今後の施策の一層の拡充を図っていきたいと考えている。 |
リンク